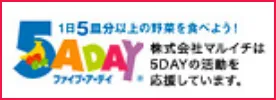感謝文
令和5年9月2日
お客様、ありがとうございます。
野菜は皆、大地に根を下ろしています。言い換えれば大地の成分が体を作っている。つまり野菜のいちばん重要なことは大地の成分が含まれているということです。ライオンがシマウマを殺しますと、まずはお尻の方から穴を開けて内蔵、特に胃袋を最初に食べます。肉食動物と言っても植物の含んでいる栄養を必要としているのです。
彼らの歯は草を食べるのに適していません。だから、動物を倒して食べるときには、その肉にあるタンパク質はもちろんですが、胃袋の中にある草も必要なのです。地球に暮らす生物はすべて、地球との関わり合いを持って生まれ、生きてきたわけですから、地球を食べて生きてゆかねばなりません。その地球を食べる一番手っ取り早い方法が草であり野菜なのです。人間ももし野菜を食べなくなったら生きて行けないし、滅びるのです。
最近野菜を食べなくなった人間は、健康を害し、滅びへの道を歩んでいるわけです。野菜は薬、体作りに必要な栄養なのです。大地に生まれ、大地で育てられた動物たちは、大地に含まれる栄養をバランスよく食べてこそ、健康と長生きを得る事ができるのです。
元国立栄養研究所 岩尾裕之
健康で長生きするために、オーガニック野菜を。
令和5年8月26日
お客様、ありがとうございます。
人間はとかく他人の目を気にしがちですが、自然界で最高の人生を送っていくためには、ひたすら自分自身と向き合っていくことです。他の誰も、それがたとえ親であっても人生を代わりには歩けません。自分の人生の決定権は自分の手にあります。これを安易に他人や環境に委ねてしまってはいけません。また自分が気にしているほど、他人は自分に関心を持っていないことも理解することですね。仮に称賛や批判を浴びたとしても、一過性のものでありますし、その責任を誰もとってはくれません。
どうぞあなたの感性を信じてあげてください。 その感性に従って、素晴らしい夢に向かってチャレンジしていってください。そのチャレンジのエネルギーに共鳴して、推進力になるエネルギーとの出会いが実現していきます。それは人間であったり、ものであったり、愛のエネルギーであったりします。そういうエネルギーを糧にして、どんどん前に進んでいって下さい。
自分の感性を信じて、昨日の自分を超えていくチャレンジの先に、あなたの豊かな人生が実現していきますよ。
放送作家・作詞家 永六輔さんの言葉
本日のご来店心よりお待ち致しております。
令和5年8月19日
お客様、ありがとうございます。
「みんなを好きに」 金子みすゞ
私は好きになりたいな、
なんでもかんでもみいんな。
葱も、トマトも、おさかなも
残らず好きになりたいな。
うちのおかずは、みいんな、
母さまがおつくりになったもの。
私は好きになりたいな、
誰でもかれでもみいんな。
お医者さんでも、カラスでも、
残らず好きになりたいな。
世界のものはみィんな、
神さまがおつくりになったもの。
世界中のみんな、誰でもかれでも好きになって、
仲良く平和に暮らせる日が、いつ来るのだろう。
本日のご来店心よりお待ち致しております。
令和5年8月12日
お客様、ありがとうございます。
「阿弥陀経」では、今の世界は極楽の世界やというている。宗教は、何教えるかというと、有り難いということを教える。宗教のない世界には有り難いということあらへん。太陽の光は熱いのが当たり前で、明るいのが当たり前である。電車があり、乗り物を利用して方々へ行ける。それはお金出して乗るのやからって当たり前や。美味しいものを食べても金を出すで、当たり前や。親に食べさしてもらう、それは親子で当たり前や。今の世界は有り難い、喜びということがない。その喜びを教えるのが宗教である。この世の中、みんなの力によって私達は生きていく。ということは一軒の家の中でも、みんな持ちおうて、お父さんからお母さん子供とすべての者がお互いに持ち合い、助け合い、励まし合い、信じ合うて、寄り合うことによって喜びがある。家の中に調和ができると喜びになる。平和の世界になる。お互いが結構なことで、生きて結構、死んで結構。命が終わったら「お世話になりましたお先にごめん。有難うございました」と礼を言うて往けるのが大切なことなん。「有り難い」「ありがたい」というて暮らしたら極楽なん。大西良慶和上「人間はねえ」より
本日のご来店心よりお待ち致しております。
令和5年8月5日
お客様、ありがとうございます。
「生きるために食べるのか」「食べるために生きるのか」と、問われた場合「食欲のためではなく、人生の崇高な目標を掲げ、その実現のために生きなければならない。そのために食べるのである」と答えるべきであると教えられてきた。
食べることについて、いつも不足気味であった時代は、食べ物を選択する余地は少なかったけれども、病気持ちは少なかった。飽食の時代と言われる現代、糖尿病、高血圧等の成人病、ガン、幼児等のアトピー性皮膚炎、発達性障害、痴呆など、病気持ちの人がやたらに多い。
一度、病気になって病院に行くと、拷問かと疑いたくなるような検査の繰り返し、その結果、患部切除の手術。又は腹の中で化学反応を起こすのではないかと思うほどの薬漬けである。
何かが間違っているような気がする。健康を害した場合、原因を自ら究明すべきである。激しい労働か、運動不足、生活環境の悪化、暴飲暴食か。食事の内容に問題ないか、生活全般を見直すことである。今こそ、正しい食事について考えねばならない。生命力のある、健康に良い食材を、正しく料理した食生活を取り戻す時である。
本日のご来店心よりお待ち致しております。