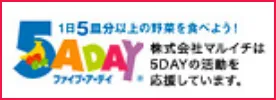感謝文
令和7年12月13日
お客様、ありがとうございます。
僕が「運」を強烈に意識するようになったのは、高校に入ってから。ある日、母親が借金取りに、土下座して謝っているのを見たんです。その時、コメディアンになってお金を稼ぎ母親のために家を建てるんだと決意したんです。しかし、高校では、辛いことばっかり。お金がなくて校則の靴も買えない、お昼のパンを買えないことも。そんな時、僕は一人で屋上に行って運について考えたんです。「辛いけど、でも運の神様は絶対見てくれている、めげずに頑張っていれば。きっと僕を有名人にしてくれるはず。だったらもっとひどくてもいいや、底辺から出発したら、僕スーパースターになっちゃうんじゃないかな」。
これが僕の運の原点。辛い時は、遠くにでっかい夢見て今の辛さに耐えようと思ったの。運の神様を信じることで。僕は生まれながらにコメディアンの才能を持ってたわけでは無いんです。
周りの人や、置かれた状況を恨まずに頑張っていたら、「運」の神様は、ちゃんと見ていてくれた。辛いときダメなときに、運はたまるのです。
萩本欽一「ダメな時ほど運はたまる」
今年、運の良かった年、又は運を貯金した年。
本日のご来店、心よりお待ちいたしております。
令和7年12月6日
お客様、ありがとうございます。
六十よりも七十だよ。
七十よりも八十、八十より九十、
九十より百、百よりは死んでからだ。
死んでからだぞ。山本玄峰老師
人間は年々、その値打ちが上がっていかなくてはならない。人間は死ぬまで修行であり、死んでからその人間の真価は定まると言われたのです。生後すぐ捨てられ、養父母に育てられました。
結婚後、暫くして眼病を患い、医師から失明宣告を受け、病気を治そうと四国八十八箇所の霊場めぐりを発願し、裸足参りをすること七回に及んだ。この四国遍路をしている間に、妻のいち女と離婚。七回目の四国遍路の途上、高知県の雪蹊寺の門前で行き倒れとなったところを山本太玄和尚に助けられ、その後仏門に入り龍沢寺住職となり、当時の米国大統領に会うなど、数奇な人生を送り、昭和二十年、鈴木貫太郎首相に終戦の詔勅にある「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」の文言を進言し終戦を勧めた。
世寿九六歳。
正月が近づいてまた一つ歳を取ると悔やんでいるあなた、玄峰老師の言葉を思い出しましょう。
本日のご来店、心よりお待ちいたしております。
令和7年11月29日
お客様、ありがとうございます。
去年の元日まだ夜も明けぬ四時頃、中一の娘を乗せて、真っ暗な道を両親の待つ故郷(佐賀)へひた走りに走っていた時のこと。巨大な木が茂っている不気味な道で、突然車が左に傾き止まりました。故障の原因もわからず、暖房もストップした車中で娘と、寒さと恐怖に震えていましたら、後方から車の灯りが近づいてきました。私はとっさに懐中電灯をもち、「止まって、お願いです」と必死に祈りながら上下左右に大きく振りました。
運が良かったのです。近づいた車がスーッと止まり、中から二十歳過ぎと思われる青年が降りてきました。娘と二人抱き合ってバンザイをして喜びました。調べて貰うと「パンクですよ」と。
「僕の車の中に入って、体を温めてください。修理は引き受けました」と言いながら、遠慮する私達を車の中へ押し込み、真っ暗で凍り付くような寒さの中、道路に直接寝転びながら懐中電灯を照らし、かじかんだ手に息を吹きかけながら修理してくださいました。「当たり前のことですよ」と、名前も教えて貰えず、後悔ばかりです。あんなに美しい心の方ですから、きっとお幸せな毎日を過ごされていると思っています。(小さな親切本部)
本日のご来店心よりお待ちいたしております。
令和7年11月22日
お客様、ありがとうございます。
平成七年十一月二十二日、マルイチとしては、初めてのショッピングセンターであり、売場面積五百坪のモデル型スーパーマーケットとして、延岡市大門町に出店しました。
競合も少なく、順調にいけると思っていたのですが、翌日の二十三日、ダイエーのハイパーマートオープン。翌年の四月にジャスコ。七月に日向のスーパーハテンコー。九月に、一キロの至近距離でマックスバリューが出店してきました。
既存スーパーが寿屋、佐伯のマルミヤストアを含め五店舗、三キロ商圏で九店舗の激戦です。
それから四年、大赤字が続き、巷ではマルイチは潰れるとの噂さえ流れました。
開店以来三十年、大阪の関西スーパーの創業者北野祐次会長にご指導を受けながら、徐々に売上を伸ばし、五年目でやっと黒字化できました。
今は県内九店舗、途中で社長も代替わりしました。企業は永続する事が一番の使命。さらに前進する為に学び続け、地域のお客様に愛される大門店を目指して従業員一同頑張って参ります。
これからもよろしくお願い申し上げます。
本日のご来店、心よりお待ちいたしております。
令和7年11月15日
お客様、ありがとうございます。
「ただいるだけで」相田みつを
あなたがそこに ただいるだけで
その場の空気が あかるくなる
あなたがそこに ただいるだけで
みんなのこころが やすらぐ
そんなあなたに わたしもなりたい
良寛和尚逸話選から
良寛和尚が、私の家に二晩宿泊された時のことだ。上の者も下の者も仲良くし、和やかな雰囲気で家は満たされた。和尚が帰った後も、その雰囲気は数日の間残り、家の者は自然と和やかであった。和尚と一晩話をすれば胸の内が清められるような思いがした。和尚はお教や書物等を読んで説教されるということは全くなく、ある時は台所で火を焚いたり、ある時は座敷で坐禅をしておられた。難しい詩文の話や道徳の話などもされず、ゆったりとしておられて、これと言って特筆すべき言動もなかった。ただ、和尚の醸し出す道徳が、自然と人々を教え導いていた。
師、余が家に信宿日を重ぬ。上下自ら和睦し、和気家に充ち、帰り去ると言えども、数日の内、人自ら和す。師と語る事一夕すれば、胸襟清き事を覚ゆ。 (後略)良寛和尚逸話選原文
本日のご来店、心よりお待ちいたしております。